
古い家の建具リフォームで新しい暮らしを!江戸川区の建具職人が教える成功のポイント

こんにちは。株式会社共進産業の吉田です。建具一筋40年以上、数多くのお宅の建具リフォームを手がけてまいりました。
最近、築30年、40年を超える古い家にお住まいの方から「建具が古くなって開閉しづらい」「隙間風が入ってくる」「デザインが古臭くて部屋全体の雰囲気に合わない」といったご相談を多くいただきます。古い家の建具リフォームは、見た目の印象を大きく変えるだけでなく、住み心地も劇的に改善できる、実は非常にコストパフォーマンスの高いリフォームなのです。
今日は、江戸川区の建具専門店として長年培ってきた経験をもとに、古い家の建具リフォームを成功させるポイントを詳しくお伝えします。
なぜ今、古い家の建具リフォームが注目されているのか
近年、新築ではなく既存の住宅をリノベーションして住み続ける方が増えています。特に東京都内では、立地の良い古い家を購入してリフォームするケースが多く見られます。
建具は部屋と部屋を仕切る重要な要素であり、家の中で最も視界に入る部分の一つです。古い建具をそのままにしておくと、どんなに壁紙や床を新しくしても、どこか古めかしい印象が残ってしまいます。逆に言えば、建具を一新するだけで、家全体の雰囲気をガラリと変えることができるのです。
また、古い建具には以下のような問題が発生しがちです。
- 木材の経年劣化による反りや歪み
- 建て付けが悪くなり、開閉がスムーズでない
- 隙間からの冷気や熱気の侵入
- 襖紙や障子紙の破れや変色
- 取っ手や引手の破損
これらの問題は、単に見た目だけでなく、省エネ性能や生活の快適性にも直結します。
古い家の建具リフォーム:選び方の重要ポイント
40年以上この業界に携わってきた経験から、建具リフォームを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
1. 家全体のインテリアとの調和を考える
建具は単体で存在するのではなく、インテリア全体の一部として機能します。床材、壁紙、家具との色合いやデザインの統一感を意識することが大切です。
例えば、フローリングがダークブラウンの場合、建具も同系色にすることで落ち着いた空間になります。一方、北欧風の明るいインテリアを目指すなら、ホワイトオークやメープルなどの明るい木材がおすすめです。
私がよくお客様にアドバイスするのは、**「建具は脇役であり主役」**という考え方です。主張しすぎず、でも存在感があり、空間全体を引き締める。そんな建具選びが理想的です。
2. 既存の枠を活かせるかどうかを確認
古い家のリフォームで気になるのがコストですよね。実は、既存の建具枠(ドア枠や鴨居、敷居など)が健全であれば、それを活かして建具本体だけを交換することで、コストを大幅に抑えられます。
ただし、枠自体が歪んでいたり、腐食していたりする場合は、枠から全て交換する必要があります。この判断は専門家でないと難しいため、まずは現地調査をおすすめします。
江戸川区や近隣の東京・神奈川(一部)・千葉・埼玉エリアであれば、私たち共進産業が無料で現地調査にお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。
3. 使い勝手と動線を考慮する
建具を選ぶ際、デザインだけでなく使い勝手や生活動線も重要です。
例えば、引き戸は開閉に場所を取らず、高齢者や車椅子の方にも優しい造りです。開き戸は気密性が高く、防音や冷暖房効率に優れています。折れ戸は限られたスペースでも開口部を広く取れます。
古い家では和室が多く、襖や障子が使われていることが一般的です。和室を洋室にリフォームする際、引き戸の良さを残しつつ、洋風デザインの引き戸に変更するという選択肢も人気です。
4. 素材選びで差がつく耐久性とメンテナンス性
木製建具専門店として、私は無垢材の建具の素晴らしさを日々実感していますが、お客様のライフスタイルに合わせた素材選びが重要です。
無垢材は、天然木ならではの風合い、調湿効果、経年変化の美しさが魅力です。突板は、無垢材の風合いを保ちながら、反りや歪みが少なく安定性が高い素材です。シート仕上げは、お手入れが簡単で、価格も抑えられます。
特に古い家の建具リフォームでは、家の歴史や味わいを大切にしたいという方が多く、無垢材や突板の人気が高いです。木の温もりは、新建材では出せない独特の雰囲気を醸し出します。
おすすめの建具スタイルと素材の組み合わせ
ここからは、私がこれまで手がけてきた古い家のリフォーム事例から、特に好評だったスタイルをご紹介します。
和モダンスタイル
日本家屋の良さを残しつつ、現代的な暮らしにマッチさせる和モダンスタイルは、ここ数年で最も人気のあるスタイルです。
格子デザインの引き戸は、伝統的な格子を現代風にアレンジしたものです。ダークトーンの木材では、ウォールナットやチークなど、重厚感のある色合いが人気です。
江戸川区のような下町エリアでは、古き良き日本家屋が多く残っており、その雰囲気を活かしながらモダンにアップデートしたいというご要望をよくいただきます。
ナチュラル・北欧スタイル
明るく開放的な空間を好む方には、ナチュラル・北欧スタイルがおすすめです。
ホワイトオークやメープルは明るい木目が特徴です。シンプルなデザインでは、装飾を抑えた直線的なラインが好まれます。ガラス入り建具は、光を通して空間を広く見せる効果があります。
このスタイルは、狭めの空間でも圧迫感を与えず、インテリア全体を明るく軽やかに見せる効果があります。
クラシック・レトロスタイル
古い家の味わいをあえて強調するクラシック・レトロスタイルも根強い人気があります。
アンティーク調の金物として、真鍮製の引手や取っ手が人気です。ガラス入り框戸は、昭和レトロな雰囲気を演出します。濃い色の木材では、マホガニーやチークが選ばれています。
特にカフェ風のインテリアを目指す方や、ヴィンテージ家具がお好きな方に好まれます。
建具リフォームの実際の流れ
「建具リフォームって、どのくらいの期間がかかるの?」という質問をよくいただきます。ここで、私たち共進産業での標準的な流れをご紹介します。
1. 無料相談・現地調査(所要時間:1〜2時間)
お客様のご要望をお聞きしながら、現状の建具を確認します。採寸も同時に行います。
2. プラン提案・お見積もり(3〜5日後)
ご要望に合わせた建具のデザイン案と、詳細なお見積もりをご提示します。
3. 発注・製作(2〜4週間)
オーダーメイドの建具を、熟練職人が一つひとつ丁寧に製作します。
4. 取り付け工事(1日〜2日)
現場での微調整を行いながら、精密に取り付けます。
5. アフターフォロー
取り付け後も、万が一の不具合や調整が必要な場合は迅速に対応します。
木製建具は生きています。季節による湿度変化で多少の伸縮があることもありますが、それも無垢材ならではの特性です。私たちは、そうした木の特性を理解した上での細やかな調整にも対応しています。
古い家の建具リフォームでは、家の構造に合わせた微調整が必要なケースが多く、既製品では対応しきれないことがあります。オーダーメイドだからこそ、ぴったりと収まり、長く快適に使えるのです。
江戸川区周辺での建具リフォーム事例
最後に、私たちが手がけた実際の事例をいくつかご紹介します。
江戸川区北小岩のK様邸(築35年)では、和室3部屋の襖を、和モダンな引き戸に全交換しました。格子デザインを取り入れることで、日本家屋の良さを残しつつ、お孫さんが遊びに来ても破れる心配のない仕様に。「家全体の印象が一新された」と大変喜んでいただきました。
葛飾区のM様邸(築40年)では、玄関から廊下にかけての建具を全面リフォームしました。特に玄関の引き戸は、断熱性の高い仕様にすることで、冬の寒さが大幅に改善されたそうです。
千葉県市川市のS様邸(築30年)では、リビングと和室を仕切る襖を、両面ガラス入りの引き戸に変更しました。光が通るようになり、閉めていても圧迫感がなく、空間を広く感じられると好評でした。
まとめ:古い家の建具リフォームで、新しい暮らしの第一歩を
古い家の建具リフォームは、家全体の印象を変え、住み心地を向上させる、非常に効果的なリフォームです。特に江戸川区をはじめとする東京都内の古い住宅では、建具を新しくするだけで、家に新しい命を吹き込むことができます。
40年以上この仕事に携わってきて感じるのは、建具には「家族の歴史」が刻まれているということです。子どもが小さい頃に落書きした跡、毎日の開け閉めで手垢がついた引手。そんな思い出を大切にしながら、でも新しい暮らしに合わせて変えていく。それが建具リフォームの醍醐味だと思っています。
もし、古い建具のことでお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。東京・神奈川(一部)・千葉・埼玉エリアであれば、私たち共進産業が現地調査にお伺いし、お客様に最適なご提案をさせていただきます。
見積もりは無料です。「ちょっと見てもらうだけ」でも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
株式会社 共進産業|東京・埼玉・神奈川・千葉の木製建具専門店
〒133-0051 東京都江戸川区北小岩8-4-20
対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉(一部地域を除く)
Email:yosida@kyoushinsangyou.jp
TEL:03-3673-1152
業界歴40年以上の職人・吉田が、責任を持って対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
古い家リフォーム, 建具リフォーム, 江戸川区建具, 木製建具, 和モダンインテリア, 建具専門店, 東京建具, インテリアリフォーム, 古民家再生, オーダーメイド建具
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。






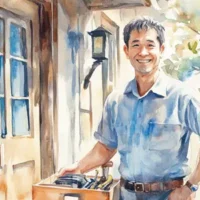

この記事へのコメントはありません。